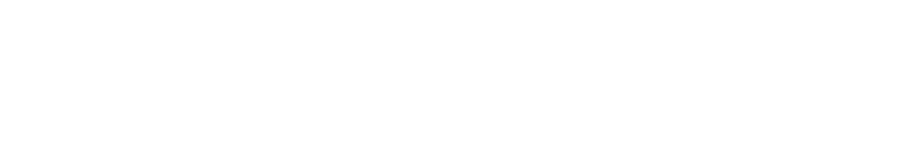塗装の素地ごしらえとは?分類や素材別に見る工程を解説
著者:山内塗装店
塗装前の素地ごしらえで、こんな不安を抱えていませんか?
「どこまで下地を処理すれば塗料が長持ちするのか分からない」「ケレンって本当に必要?」「作業後すぐ剥がれたらどうしよう…」。現場ではそんな声が多く聞かれます。素地調整が不十分なまま塗装を進めると、塗膜の付着力が低下し、数年で剥離や膨れが発生するリスクがあります。
素地処理の品質が塗装全体の寿命に大きな影響を与えるとはいえ、モルタル、金属、石膏ボードなど素材ごとに適切な処理方法や工程が異なるため、下地処理の「正解」が分かりにくいのも事実です。そこで本記事では、素地ごしらえの基本から下地種別ごとの調整方法、ケレン種別などを解説します。
山内塗装店は、外壁や屋根の塗装を通じて、お客様の大切な住まいが長く快適に過ごせるよう、日々取り組んでいます。塗装においては、下地処理をはじめ、ウレタン塗装やシリコン塗装など、多様な技術と知識を活かし、質の高い仕上がりを心がけています。また、施工後もお客様との信頼関係を大切にし、アフターフォローまでしっかり対応いたします。住まいの塗装でお悩みやご相談がありましたら、どうぞ山内塗装店にお任せください。一人ひとりのお客様のご要望やお住まいの状態を丁寧に把握し、安心していただけるよう、誠実に取り組んでまいります。

| 山内塗装店 | |
|---|---|
| 住所 | 〒061-3203北海道石狩市花川南3条1丁目67 |
| 電話 | 0133-72-7811 |
塗装における「素地ごしらえ」とは?目的をやさしく解説
なぜ塗装前に素地ごしらえが必要なのか?
素地ごしらえ(そじごしらえ)は、塗装工程の中でも基礎を作る非常に重要な準備作業の一つであり、コンクリート、金属、木材、石膏ボードなど塗装対象となる素材の表面(素地)を整えることで塗料の効果を最大限に引き出すことを目的としています。
塗装前に素地ごしらえを行う最大の目的は、塗料の付着性を高めることです。汚れやサビ、旧塗膜などが残った状態で塗料を塗布すると、塗膜の浮き・剥がれ・ムラなどが起きやすくなり、塗り替え直後の不具合や再施工の手間につながります。
さらに、塗膜の耐久性にも大きく影響します。素地が整っていないと、湿気や紫外線の影響を受けやすく、塗装が早期に劣化します。特に外壁や屋根など屋外環境にさらされる部位では、塗装の持ちを左右する非常に重要な工程となります。
素地ごしらえを怠った場合の不具合例
| 処理不足の内容 | 想定される不具合 |
| 表面洗浄が不十分 | 塗料の密着不良、剥がれ |
| サビや旧塗膜の除去不足 | サビの再発、膨れ、塗膜剥離 |
| 乾燥不足 | 塗膜が硬化せずベタつき、変色する可能性 |
| 凸凹や割れの放置 | 美観の低下、仕上がりの粗さ |
また、素地ごしらえの有無は見積金額や工期にも影響します。見積書に「素地調整込み」とあるかを必ず確認することで、後からの追加費用やトラブルを回避できます。
素地ごしらえは施工業者の技術レベルが試される工程でもあり、丁寧な処理を行うには、素材ごとの特性理解と、適切な道具・処理剤の選定が欠かせません
現場で重要視される要素
- 使用される塗料の種類と素地の相性
- 天候や気温、湿度による乾燥時間の管理
- 吸水性の高い素材への下塗り材の選定
- 金属面ではグラインダーやサンドペーパーなどの選択
これらを適切に管理しながら行う素地ごしらえは、塗装の質を格段に高めます。素地ごしらえが「施工後すぐには見えないが、数年後に差が出る」工程であることを意識し、信頼できる施工業者に任せることが重要です。
素地ごしらえの分類と具体的工程
A種・B種・C種の違いと使い分け
素地ごしらえは、内容や目的に応じて「A種・B種・C種」の3つに分類され、建築塗装や金属塗装、石膏ボードなど幅広い素材に対する前処理として適用されています。
素地ごしらえの分類と特徴
| 種類 | 内容 | 目的 | 主な適用対象 | 使用例 |
| A種 | 既存塗膜やサビを完全に除去する | 塗膜の密着性を最大化し、長期耐久性を確保 | 金属、鉄部、劣化塗装面 | 鉄骨階段、鉄扉、防水塗装下地など |
| B種 | 軽度なケレンや浮き・汚れを除去し表面を調整 | 塗料の付着を確保し、表面の凹凸を調整 | 外壁、石膏ボード、塩ビシート面 | モルタル外壁、下地補修後の仕上げ塗装 |
| C種 | 高圧洗浄や拭き取り等による簡易洗浄のみ | 表面のホコリ・油分・付着物の除去 | 比較的状態の良い下地 | 内装の再塗装、軽微な補修範囲 |
適切な素地ごしらえの種別を選ぶことは、塗膜の長寿命化や美観維持に直結します。工事費用だけで判断せず、素地の状態と目的を正確に把握し、最適な種別を選ぶ判断力が求められます。
施工現場での素地ごしらえ工程の実際例
塗装現場では、素地ごしらえは単なる下準備ではなく、最終仕上がりを左右する重要な工程です。作業の丁寧さや順序の正確さにより、塗装後の密着性・耐久性・美観が大きく左右されます。
一般的な素地ごしらえ工程と注意点
| 工程順序 | 作業内容 | 使用道具・機材 | 注意点 |
| 1 | 高圧洗浄 | 高圧洗浄機 | 汚れ・コケ・カビ・劣化塗膜の除去。乾燥時間を必ず確保する |
| 2 | ケレン(B種・A種) | スクレーパー、ワイヤーブラシ、サンダー | 塗膜の浮き、サビ、ひび割れなどの除去。施工範囲を見極める |
| 3 | パテ補修・下地補正 | パテ材、補修モルタル | クラックや欠損部を修復。後の塗装面の平滑化に直結 |
| 4 | 乾燥・養生 | 養生シート、乾燥ブロワーなど | 湿気が残ると塗膜不良に直結。完全乾燥を確認する |
| 5 | プライマー塗布(下塗り) | ローラー、刷毛 | 表面を均一化し塗料の密着性を向上させる。素材に適した製品選定が必要 |
上記のような工程を経ることで、塗料の性能を最大限に引き出すことができます。特に外壁や屋根など、風雨や紫外線にさらされる部分では、素地調整の精度が経年劣化のスピードに直結します。
これらの作業は、すべてが連動しているため、一工程でも疎かにすると最終的な塗膜性能や仕上がりに悪影響を及ぼします。経験豊富な職人による一貫した現場管理と確実な作業の積み重ねが、塗装品質の差を生み出します。見積もり段階で工程の有無や詳細を確認することも、発注者としての大切な判断基準の一つです。
素材別に見る素地ごしらえのポイントと注意点
モルタル・サイディングの場合の素地調整
モルタルやサイディング外壁には、吸水性やクラック、欠損といった特有のリスクがあるため、それぞれの特性に合った下地調整が求められます。
モルタルとサイディングにおける主な素地ごしらえ内容
| 項目 | モルタル外壁 | サイディング外壁 |
| 吸水性 | 高い | 比較的低いが、チョーキングに注意 |
| クラック対応 | フィラー・シーリング・Uカットなど | クラックは少ないが目地処理が重要 |
| 素地調整方法 | ケレン・下地調整・補修 | 洗浄・目地補修・シーラー塗布 |
| 下塗り材 | 弾性フィラー、微弾性シーラーなど | シーラー(浸透型・密着型) |
| 注意点 | 湿度管理、吸水調整 | 目地のコーキング打ち替えが必須 |
このように、モルタルとサイディングは素材の性質や劣化の仕方が異なるため、それぞれに適した下地処理と下塗り材の選定が、塗装の品質を長く維持するためのカギとなります。とくに気温差・湿度変化の激しい地域では、素地の状態管理がより重要になります。
鉄部・金属面のサビ落としと防錆処理
鉄部や金属面の塗装において、サビの処理と防錆対策は、塗装の寿命を左右する極めて重要な工程です。早期の剥離や素地の腐食の進行を防ぐためにも、塗装前の「素地ごしらえ」としてのケレン作業と適切な防錆処理は不可欠です。
金属素地の処理に使用される「ケレン」は、作業の徹底度に応じて「1種〜4種」に分類されます。
それぞれのケレン種別とその特徴
| ケレンの種別 | 処理方法の概要 | 主な使用シーン |
| 1種ケレン | ブラスト処理による全面除去 | 発錆が著しく新築・重防食工事など |
| 2種ケレン | ディスクグラインダーや電動工具での研磨除去 | 一般的な中程度の錆落とし |
| 3種ケレン | 手工具(ワイヤーブラシなど)での軽度除去 | 軽微なサビや旧塗膜の処理 |
| 4種ケレン | 高圧洗浄や布拭きなど簡易な表面清掃 | 目立つ錆がない場合の塗替え前処理 |
特にリフォームや再塗装の現場では、2種〜3種ケレンが多く採用されます。ディスクグラインダー・サンダー・ワイヤーブラシなどの工具を用いることで、錆とともに、表面の凹凸や汚れ、油分、塗膜の浮きを効果的に除去し、下塗り塗料の密着性を高めることができます。
次に重要なのが、防錆下塗りの選定です。ケレン後の鉄部は非常に錆びやすいため、処理後すぐに下塗り材を塗布する必要があります。一般的な防錆下塗りには以下のような種類があります。
- エポキシ系さび止め塗料 密着力と耐薬品性に優れ、外部金属部に多用される
- 変性エポキシプライマー 高耐候性で住宅外装に適する
- 一液型防錆プライマー 小規模現場やDIY向けで扱いやすい
これらの防錆塗料は、素材の種類や使用環境、重防食の必要性に応じて選定されるべきです。特に海岸部や積雪地域など、過酷な自然条件下にある建物では、高耐久な2液型防錆塗料が推奨されることもあります。
また、鉄部塗装では周囲との接合部(溶接痕やビスまわり)に錆が集中しやすいため、局所的な補強処理や錆止めの二度塗りなど、細部の処理も忘れてはなりません。
金属素地への施工時の注意点
- ケレン後はすぐに防錆下塗りを行い、酸化による再発錆を防止する
- 下塗りと上塗りの乾燥時間を十分に確保し、塗膜の不具合を防ぐ
- 同一金属種であっても、劣化状態によって処理内容を見極めること
これらの工程を省略すると、施工後数ヶ月で塗膜の浮きや剥離、再発錆が発生しやすくなり、結果的に再工事コストや信頼の低下につながります。
鉄部や金属面の塗装において、適切な素地ごしらえの処理を行うことで、施工後の美観と耐久性を飛躍的に高め、長期的なメンテナンスコストの削減にもつながります。
石膏ボード・木部などデリケートな素地の対処法
石膏ボードや木部は、塗装において特に慎重な下地調整が求められる「デリケートな素地」に該当します。これらの素材は吸水性が高く、微細な粉塵(チョーキング)や繊維の剥離が起こりやすいため、処理を怠ると塗膜の密着不良や仕上がりのムラにつながる恐れがあります。
石膏ボードの特性と処理ポイント
| 処理対象 | 特性 | 主なリスク | 推奨処理内容 |
| 石膏ボード | 多孔質・吸水性高い | 表面の剥離・塗料の過吸収 | 専用シーラー塗布・下地処理材での均一化 |
| パテ跡 | 吸水ムラ・割れやすい | 塗膜ムラ・クラック | パテ研磨→吸水調整シーラー処理 |
| 面取り部 | 角落ちしやすい | エッジの浮き・ひび割れ | パテ補修+養生+下塗り強化 |
石膏ボードはその構造上、表面が非常に吸水しやすいため、下塗りとして「吸水抑制型シーラー」を使用することが基本です。これにより、上塗り塗料の吸収を防ぎ、塗膜の均一性と仕上がりの美しさが確保されます。特にEP(エマルションペイント)やAEP(アクリルエマルションペイント)を使用する際は、下地が塗料を吸いすぎると色ムラや艶ムラが発生しやすくなるため注意が必要です。
一方、木部もまた、温度や湿度の影響を受けやすく、含水率の変化によって塗膜がひび割れやすくなるという特徴を持っています。木部の素地ごしらえでは以下の工程が重要です。
- 表面研磨(サンディング)による毛羽立ち除去
- 汚れ・油分のふき取り
- 節やヤニの抑制(シーラーやシミ止め塗料使用)
- 防腐・防虫処理の確認
木部も石膏ボードと同様にB種処理の対象となるケースが多く、軽度なケレン作業や吸水調整、表面強化が主な目的となります。古い木部では、粉状の塗膜劣化が進行しやすいため、表面の水洗いや中性洗剤での洗浄後、完全乾燥させたうえで処理を行います。
加えて、近年は「吸水調整+防カビ・防藻効果」を併せ持つ多機能下地材も登場しており、湿気の多い部屋や木造住宅への採用が増えています。木部や石膏ボードにおける吸水コントロールは、見た目の美しさだけでなく、塗膜の密着性や長期耐久性にも直結するため、下地処理は単なる準備工程ではなく、塗装品質を左右する「核」とも言えるのです。
木部も石膏ボードへの施工時の注意点
- 石膏ボードは「パテ研磨後」の粉塵除去が不十分だと、密着不良を起こす
- 木部は含水率20%以下を目安にし、湿気が多い日は避ける
- 節のヤニには「シミ止めシーラー」を使用し、再発を防ぐ
- 吸水性の高い素地には、シーラーを2回塗りすることも選択肢となる
デリケートな素材ほど、見えない部分の工程が品質に直結します。プロによる適切な素地ごしらえを行うことで、塗装後の色持ちや耐久性が大きく変わり、結果として施工後のクレーム減少やお客様満足度の向上にもつながるのです。
素地ごしらえを成功させるチェックリスト
作業前に行うべき現場確認と素材ごとの対策
塗装工程において「素地ごしらえ」は仕上がりの良否を左右する極めて重要な作業であり、その第一歩が「作業前の現場確認」です。現場ごとに素材や劣化状況が異なるため、塗装業者やDIYユーザーにとって的確なチェックと素材別の対策は不可欠です。
主要素材ごとの確認ポイントと対策
| 素材 | 確認ポイント | 推奨対策 |
| モルタル外壁 | ヘアクラック・欠損・白華現象 | クラック補修・高圧洗浄・下地強化材 |
| 窯業系サイディング | チョーキング・浮き・反り | 洗浄・部分交換・シーリング再施工 |
| トタン・鉄部 | サビ・膨れ・前塗膜の浮き | ケレン・サビ止め・下塗り適正化 |
| 木部 | 吸水跡・劣化・灰汁汚れ | ペーパー掛け・灰汁洗い・下地強化 |
| 石膏ボード | 吸水・カビ・脆弱な表面 | 吸水抑制材処理・下地材補強 |
塗装を成功に導くためには、この作業前の段階でどれだけ「正確に素材と状態を把握できるか」が鍵となります。素材ごとの対応策が明確であるほど、次工程の「乾燥・下塗り・仕上げ」がスムーズに進行し、耐久性や見栄えのよい塗膜形成につながります。
作業中に確保すべき温度・湿度管理、乾燥時間
塗料の性能を最大限に活かすため、素地ごしらえの工程中に最も注意すべきポイントのひとつが、作業環境の「温度」「湿度」そして「乾燥条件」です。
塗装時の環境基準とその理由
| 項目 | 推奨値 | 理由 |
| 気温 | 5℃〜35℃ | 低温では塗料が硬化不良、高温では早乾しやすい |
| 湿度 | 85%以下 | 高湿度は塗膜の膨れや白化を引き起こす |
| 露点差 | 表面温度との差が3℃以上必要 | 結露による密着不良を防ぐ |
| 風速 | 3m/s以下 | 風で塵や砂が付着すると塗膜が不均一になる |
| 直射日光 | 避けることが望ましい | 塗膜が急乾して収縮や割れが発生しやすい |
とくに乾燥時間の確保は、仕上がりを左右する最重要項目です。素地調整直後に下塗りを行うと、下地に含まれた水分や洗浄残りが原因で、塗料の劣化リスクが高まります。
素地別の乾燥時間目安(標準的な条件下)
| 素材 | 最低乾燥時間の目安 | 補足条件 |
| モルタル | 24時間以上 | 含水率10%以下が理想 |
| コンクリート | 3〜7日 | 気温20℃前後、雨天不可 |
| 木部 | 12時間以上 | 高温多湿の場合は延長 |
| 金属部(ケレン後) | 表面が完全乾燥するまで | 水洗い後は速やかに乾拭き・乾燥 |
| 石膏ボード | 8〜12時間 | 室内施工時は換気と除湿機併用が効果的 |
塗装作業は「ただ塗る」だけではなく、環境管理と見極めが品質を大きく左右します。特に梅雨時期や冬場の施工では、工程管理の甘さが後の剥離・浮き・膨れといった重大な施工不良につながりやすく、慎重な判断が求められます。
作業後に行う下塗り前の表面確認と付着テスト
素地ごしらえを終えた後の「表面確認」と「付着テスト」は、塗装工程において極めて重要なステップです。塗膜の剥がれや膨れといった重大な施工不良を未然に防ぐために、作業後の検査工程を厳密に実施する必要があります。
素地ごしらえ後に確認すべきチェック項目
| チェック内容 | 詳細説明 | 不備時の影響例 |
| 表面の乾燥状態 | 表面が湿っていないか、指触で確認 | 塗膜の膨れ・剥がれの原因 |
| 汚れや粉塵の有無 | 風や施工時の粉塵が付着していないか | 密着不良・ムラの発生 |
| 錆び・油分の再発 | 金属部や鉄部に新たな錆・油が浮いていないか | 防錆効果の減少・変色 |
| ケレン状態 | 均一にケレンができているか、研磨不十分箇所の確認 | 塗膜の密着ムラ |
| 含水率 | 木部やモルタルなどの含水率が適正か | 施工後の水分蒸発による膨れ |
作業後のチェックで不備が見つかれば、必ず再度のケレン・清掃・乾燥処理を行い、再確認を経て次工程へ進むことが原則です。この一手間を惜しまず、丁寧に仕上げることが、高品質な塗装施工へとつながります。
まとめ
塗装の仕上がりや耐久性を大きく左右するのが「素地ごしらえ」です。どれだけ良質な塗料を使っても、下地が整っていないと、剥がれや浮きが起こりやすくなり、結果的に早期の再施工が必要になるリスクがあります。
素材によって適切な処理方法は異なります。モルタルや金属、石膏ボードなど、それぞれに合った下地調整やケレンの方法を選ぶことが、塗装の長持ちにつながります。
今回ご紹介したポイントを押さえれば、塗膜の密着性を高め、余計な補修費を防ぐことができます。見えない工程こそ丁寧に行うことが、安心で高品質な塗装工事の第一歩です。
山内塗装店は、外壁や屋根の塗装を通じて、お客様の大切な住まいが長く快適に過ごせるよう、日々取り組んでいます。塗装においては、下地処理をはじめ、ウレタン塗装やシリコン塗装など、多様な技術と知識を活かし、質の高い仕上がりを心がけています。また、施工後もお客様との信頼関係を大切にし、アフターフォローまでしっかり対応いたします。住まいの塗装でお悩みやご相談がありましたら、どうぞ山内塗装店にお任せください。一人ひとりのお客様のご要望やお住まいの状態を丁寧に把握し、安心していただけるよう、誠実に取り組んでまいります。

| 山内塗装店 | |
|---|---|
| 住所 | 〒061-3203北海道石狩市花川南3条1丁目67 |
| 電話 | 0133-72-7811 |
よくある質問
Q. 素地ごしらえの費用は塗装工事全体のどれくらいを占めるのですか?
A. 素地ごしらえにかかる費用は、外壁塗装全体の工事費用の中でおよそ10%から20%を占めることが多く、建物の状態や素材、必要な処理内容によって変動します。たとえば、金属面での1種ケレンやモルタルの欠損補修など、塗膜の密着性を高めるための処理が必要な場合、相応の作業費がかかります。地ごしらえが不十分だと塗装のやり直しに繋がる可能性が高く、結果的に余計なコストが発生するリスクもあるため、初期段階での適正な処理が費用対効果に優れた判断となります。
Q. モルタルやサイディングなど、素材ごとに素地調整はどう違うのですか?
A. モルタルは吸水性が高く、表面のひび割れや欠損が見られやすいため、下地調整にはクラック補修やパターン復元が含まれます。対してサイディングの場合はチョーキング除去や目地部のシーリングが主な調整項目です。塗料の付着性を高めるには、素地に合わせた工程を選択することが非常に重要で、B種処理やC種処理など、工程の選定は素材と劣化状況をもとに慎重に行う必要があります。これらの違いを理解しておくことで、施工品質の向上と塗膜寿命の延伸につながります。
Q. 鉄部のサビ取りではどのケレン方法が一番効果的ですか?
A. 鉄部の素地ごしらえには、劣化の進行度に応じて1種から4種までのケレン方法があります。最も効果的とされるのは1種ケレンで、これは旧塗膜やサビを完全に除去するブラスト処理です。ただし、コストや工期が増えるため、部分的な処理や塗料の種類によっては2種や3種ケレンが選ばれることもあります。特に防錆処理を前提とした下塗りには、素地の状態と工程の選定が密接に関係しており、適切なケレン方法を選ばないと数年以内に塗膜剥離のリスクが高まります。
Q. 素地ごしらえをしないとどんな不具合が起きるのでしょうか?
A. 素地ごしらえを怠ると、塗膜の付着不良、早期のひび割れ、膨れ、剥離といった不具合が高確率で発生します。たとえば、素地に汚れや湿気が残ったまま塗料を塗ると、数ヶ月で塗装面に浮きが発生し、最悪の場合には下塗りからやり直す必要があります。また、下地調整が不十分なまま上塗りを行うと、塗料の性能が発揮されず、耐久性が大幅に低下することもあります。地ごしらえは仕上がりの美観だけでなく、長期的な施工品質を左右する極めて重要な工程です。
会社概要
名称・・・山内塗装店
所在地・・・〒061-3203 北海道石狩市花川南3条1丁目67
電話番号・・・0133-72-7811
シェアする